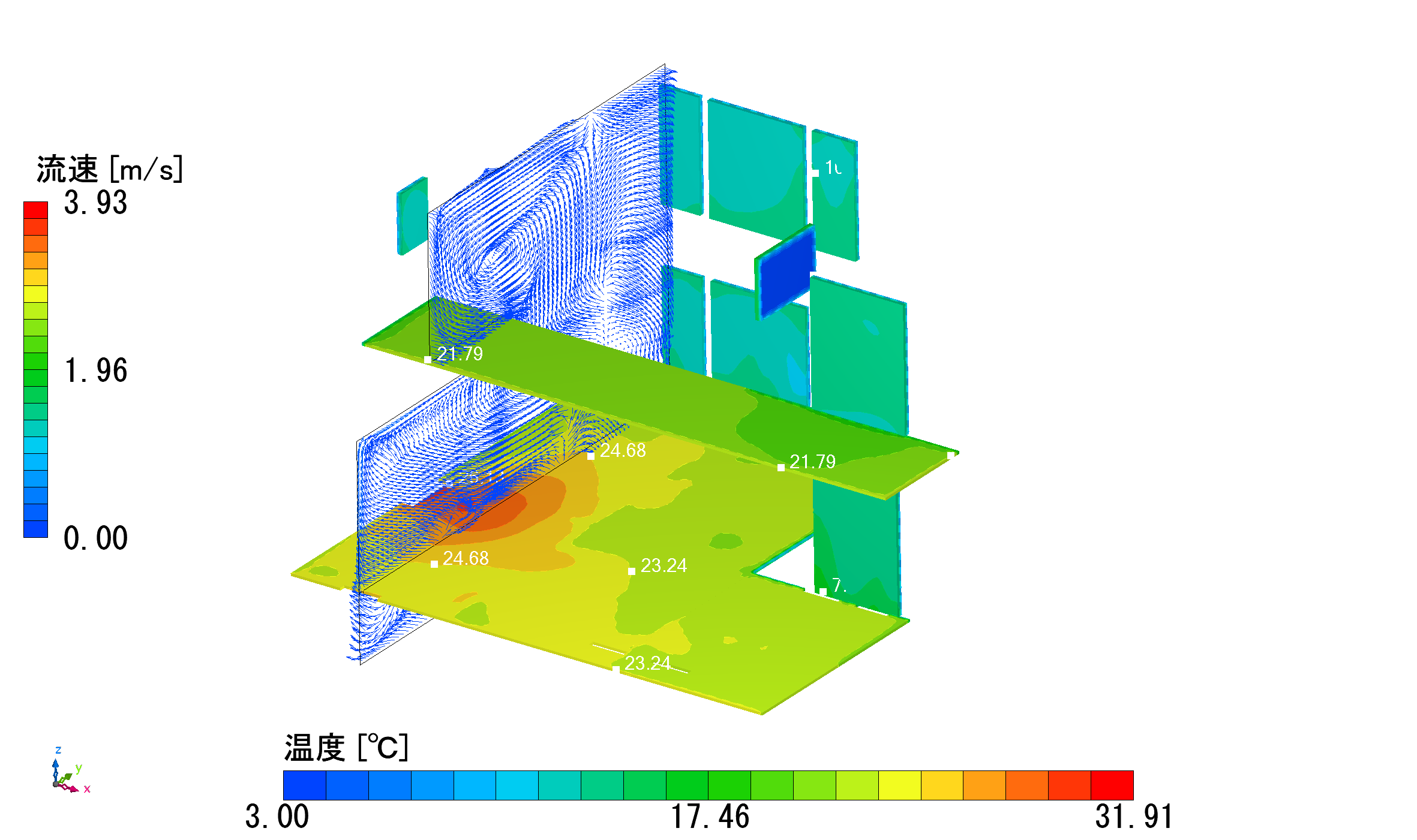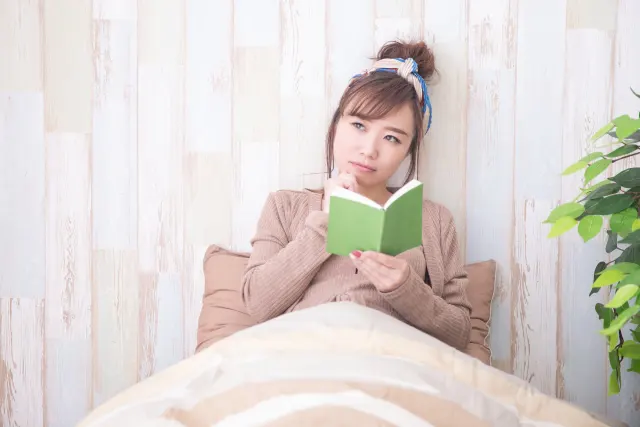新しいZEHのGX ZEHが定義されました
以前、「GX住宅が新しいZEHになる!?」と題して新しいZEH基準がスタートするという話題を提供しました。今回はこの新しいZEHが経産省によって、きちんと定義されたという内容です。経済産業省が2025年9月26日にWEBサイトに掲載した内容を要約しています。
<参考>「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」を定義しました
新しいZEHが誕生した理由

2030年以降、新しく建てられる住宅はZEH基準を上回る住宅であることが義務化される方針となっています。そして、日本が最終的に掲げる、2050年でのゼロカーボンに向けての検討が様々に行われる中、2030年に義務化されるZEHはより高い省エネルギー性能であることが必要と議論されるようになり、ZEHの定義の見直しが行われるようになってきました。
このことから、新たに誕生したZEHの名称が「GX ZEH」と定義されました。
この運用は2027年4月以降に適用するとされており、これから住宅を建てるひとのための大きなヒントとなるでしょう。
定義された様々なレベルのZEH
従来のZEHにもいくつかの種類がありましたが、今回の「GX ZEH」にも4つの種類があります。それぞれの名称が以下です。
GX ZEH+:年間の一次エネルギー消費量がマイナスの住宅
GX ZEH:年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅
Nearly GX ZEH:年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅
GX ZEH Oriented:太陽光発電の設置が無い、GX ZEHと同等の住宅。
(都市や雪の多い地域など、太陽光発電の設置に向かない地域限定)
といったような感じです。
なぜ4つの種類を用意するかというと、これらの違いによって、受けられる補助金や税制優遇に差をつける目的があると考えられます。
今までのZEHとの違い
今の基準から比べると求められる省エネルギー性能が高くなります。
このためには、主に断熱性能をG2(断熱性能等級6)以上とし、省エネルギー設備を備える必要が出てきます。
具体的な数値の違いを以下で見てみましょう。
表の中にはすでにあるGX住宅の基準も掲載しておきます。
| これまでの基準 | GX住宅の基準 | GX ZEH | |
|---|---|---|---|
| 断熱性能(大阪や東京 6地域の場合) | UA値0.60 | UA値0.46 G2性能と同じ | UA値0.46 G2性能と同じ |
| 必要な省エネ性能 | 基準から20%削減 | 基準から35%削減 | 基準から35%削減 |
| 必要な設備 | 特になし | HEMS | 定置用蓄電池 高度エネルギーマネージメント(機器の制御が可能なHEMS) |
| 太陽光発電で必要な発電量 | 100% | 100% | 100%ただし、GX ZEH+の場合115% |
これをみると、GX ZEHは設備の要件以外はGX住宅とほぼ同じ内容になっていて、前回紹介した予定段階の内容がほぼそのまま採用されています。
また、今回の定義においてもエネルギー消費量の計算対象は、暖冷房、換気、給湯、照明となっていて、従来通り、その他の家電については計算対象外となっています。(ただし、将来的に計算方法が変わった場合は、それに従うこととなっています。)
GX ZEHの設備の要件
上の表でも必要な設備を記載しましたが、従来のZEHから、GX ZEHでは新たに必要な設備が追加されました。その内容についても見ていきたいと思います。
高度エネルギーマネジメント
GX住宅ではHEMSが必須要件となっていましたが、GX ZEHでは更に高度エネルギーマネジメントが必須要件となっています。
現状のHEMSは、家の中で利用されている電気量や発電量、売電量などをモニターを通して確認することが出来るようになっています。
今回の高度エネルギーマネジメントが想定しているのは、このHEMSが更に進化して、電力の状況に応じて住宅内の冷暖房設備や給湯設備などを制御可能であることです。(一部のHEMSでは、現段階でも制御が可能です。)ただし、この制御が自動制御なのか、手動で制御出来ればよいのかについては、まだ詳細は明らかになっていません。
また、この機器は蓄電池の充電や放電の制御も必要とされています。
定置用蓄電池
今回の定義では定置用蓄電池の設置が必須となりました。これは、先程の高度エネルギーマネジメントと連携出来るものでなくてはなりません。
ただ、具体的にどの程度の容量の蓄電池が必要なのかは現段階では明記されていません。
EV充電/充電設備
GX ZEHでは推奨事項として、電気自動車用の充放電設備の検討が挙げられています。
これは、もし居住者が電気自動車を保有していない場合であっても、将来的に建物ができあがってしまった後に導入が困難とならないように、建築士が事前に説明する必要があるとされています。
つまり、もし建物を建ててしまった後に導入が困難なのであれば、事前にEV充放電設備を導入するように説明しましょうという意図があると考えられます。
これまでのZEHはどうなるのか?
GX ZEHは、2030年以降に義務化されると考えることが妥当でしょう。
ただし、従来型のZEHが2030年以降にないがしろにされることは無いようで、今後も正味のゼロエネルギー住宅としてみなされるようです。
まとめ
今回、定義が明確になりましたが、2027年の4月までは運用が開始されません。
ただ、これから2027年4月までの間に新しく家を建てる場合、断熱性能をどの程度にするべきか、設備機器をどの程度のものにするべきかの検討材料にはなりそうです。




 資料請求・お問い合わせ
資料請求・お問い合わせ
 太田(健康・高断熱住宅専門家)
太田(健康・高断熱住宅専門家)